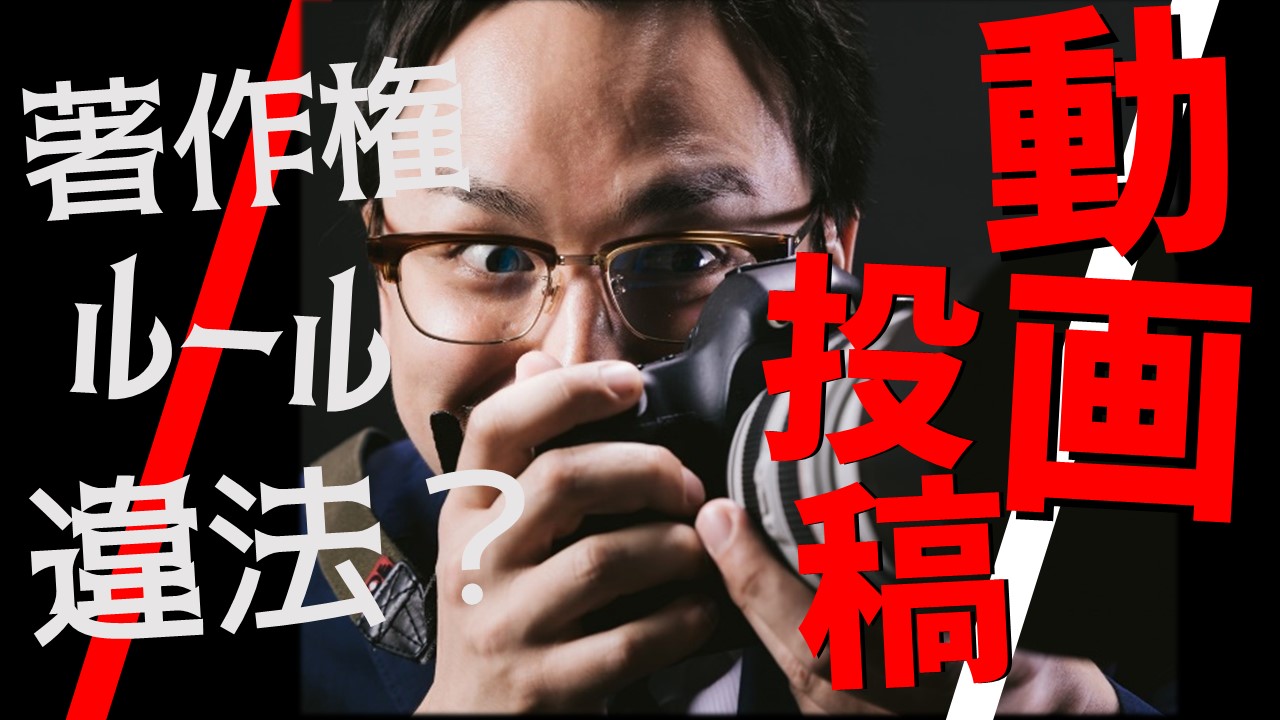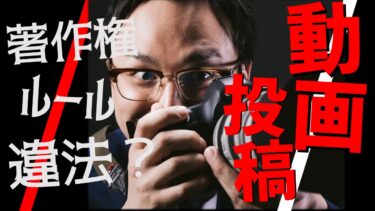「この切り抜き、他のチャンネルと丸被りだ…!これって著作権侵害にならないかな?」
YouTubeで切り抜きチャンネルを運営している、あるいはこれから始めようとしているあなたなら、一度はこんな不安を抱いたことがあるかもしれません。
特に、人気の配信者の面白いシーンは、誰もが「切り抜きたい!」と思うもの。
結果として、複数のチャンネルが全く同じ場面を切り抜くことは日常茶飯事です。
この記事では、切り抜き動画をめぐる著作権の仕組みを解説していきます。
すべての権利は「元の配信者」から始まっている
まず、絶対に忘れてはならない大原則から確認しましょう。
切り抜き動画の元となる配信(ライブ配信のアーカイブなど)の著作権は、すべて「元の配信者(原著作者)」にあります。
私たちが切り抜き動画を作成・公開できるのは、あくまで配信者本人が「私の動画を使って、切り抜き動画を作ってもいいですよ」と許諾(ライセンス)を与えてくれているからです。
この許諾があるからこそ、私たちは安心して活動できます。
切り抜き動画は、この元の配信(原著作物)を元に作られた「二次的著作物」という位置づけになります。
切り抜き動画に「新たな著作権」が生まれる瞬間とは?
「二次的著作物」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、要は「原作を元に新しく作られた作品」のことです。
そして、この二次的著作物にも、新たな著作権が発生する可能性があります。
ただし、そのためには非常に重要な条件があります。
それは、元の素材に「創作性」が加えられていることです。
著作権法は、人間の「思想又は感情を創作的に表現したもの」を保護する法律です。
つまり、誰かのアイデアや個性が表現として形になった部分に、権利が生まれるのです。
これを切り抜き動画に当てはめてみましょう。
「創作性」が認められやすい編集例
-
独自の字幕・テロップ:
-
単なる文字起こしではなく、ツッコミを入れたり、状況を分かりやすく要約したり、面白いフォントや色使いで感情を表現したりする字幕。編集者の個性が光る部分です。
-
-
効果音(SE)やBGMの追加:
-
面白い場面で「ピコーン!」という効果音を入れたり、感動的なシーンでBGMを流したりと、視聴者の感情を揺さぶるための音響演出。
-
-
画像の挿入やエフェクト:
-
会話に出てきた物事の画像を挿入して理解を助けたり、特定の人物をズームアップしたり、面白いエフェクトを加えたりする視覚的な工夫。
-
-
巧みなカット割りや構成:
-
複数の配信から特定のテーマ(例:「〇〇さんの爆笑シーンまとめ」)に沿った部分だけを集め、巧みな順番でつなぎ合わせることで、元の配信にはなかった新たなストーリーや面白さを生み出す編集。
-
ちゃんとした凝った編集をしているのであれば、「創造性」が認められる可能性があります。
「創作性」が認められにくい例
-
配信の特定の部分をただ切り取って、前後にオープニングとエンディングを付けただけの動画。
-
テロップも文字起こしのみで、特に演出がない動画。
つまり、単に配信を切り貼りしただけでは著作物とは認められにくく、そこに編集者独自の工夫やアイデアが「表現」として加わって初めて、その切り抜き動画自体に著作権が宿るのです。
1分間に1~2回程度のテロップを入れているだけ、だと厳しいかもしれないです。
ライバルと「切り抜き箇所」が同じだった場合
さて、ここまでの知識を元に、冒頭の疑問に戻りましょう。
「切り抜きチャンネルAが先に動画を作り、Bが全く同じ箇所で動画を作った」
この状況を、2つのケースに分けて考えてみます。
ケース①:著作権侵害になる可能性が高い場合
もし、チャンネルBが、Aの動画を見て…
-
Aが付けた字幕の文章、言い回し、デザインをそっくり真似た
-
Aが使った効果音やBGMを、全く同じタイミングで挿入した
-
Aが行ったズームやエフェクトなどの画面演出を丸パクリした
このような場合、BはAの「創作性が加えられた表現部分」を盗んだことになります。
これは、Aの二次的著作物としての著作権を侵害する行為であり、Aが訴えればBが負ける可能性は十分にあります。
ケース②:著作権侵害にならない場合(質問のケース)
一方で、チャンネルBが…
-
Aが切り抜いたのと同じ配信の、同じ時間帯を切り抜いた
-
しかし、字幕や効果音、構成などの編集は、すべてBが独自に行った
この場合、BはAの著作権を侵害していません。
なぜなら、AとBが共に利用しているのは、元の配信者が提供してくれた「素材」に過ぎないからです。
Aが先にその「素材」を使って料理をしたからといって、後から他の人が同じ「素材」を使って料理をすることを禁止する権利は、Aにはありません。
「配信のどの部分を切り抜くか」というアイデアや着眼点そのものには、著作権は発生しないのです。
これは、同じ絶景スポットから、別々の写真家が写真を撮るようなものです。
Aさんが先に富士山の写真を撮ったからといって、Bさんが富士山の写真を撮ることを止めさせることはできませんよね。
それぞれが、自分の構図、設定、感性で「創作」を行う限り、どちらの作品も独立した著作物として認められます。
もし訴えられても「勝つのが難しい」理由
それでもAが「Bは私を真似した!」とBを訴えたとしましょう。
この場合、裁判でAが勝つためには、以下の2点を証明する必要があります。
-
A自身の動画に、著作物として保護されるべき「創作性」があること。
-
Bが、Aの動画の「創作的な表現部分」を意図的に真似て、自分の動画を作成したこと。
「同じ箇所を切り抜いた」という事実だけでは、2つ目の証明は極めて困難です。
Bは「Aの動画は見ていない。誰がどう見てもこのシーンがハイライトなのだから、切り抜き箇所が被るのは当然だ」と主張できます。
そして、その主張は多くの場合、正当なものとして認められるでしょう。
まとめ
今回の内容をまとめましょう。
-
切り抜き動画の著作権の根源は「元の配信者」にある。
-
編集者の「創作性(独自の字幕や演出など)」が加わることで、切り抜き動画自体にも著作権が生まれる。
-
他のチャンネルと「切り抜き箇所」が被るだけでは、著作権侵害にはならない。それは同じ「素材」を使っているに過ぎない。
-
著作権侵害になるのは、字幕や効果音など、他人の「創作的な編集」を丸パクリした場合。
切り抜きチャンネル運営において、他のチャンネルと切り抜き箇所が被ることは避けられません。
それを恐れる必要は全くありません。
本当に大切なのは、「他人の編集を安易に真似するのではなく、自分だけの付加価値をどう加えるか」です。
同じ素材(配信)から、あなたにしか作れない面白い切り口、分かりやすい解説、笑えるツッコミを加えていくこと。
それこそが、視聴者に選ばれるチャンネルになるための唯一の道であり、あなた自身の「創作物」を守る最強の盾にもなるのです。
著作権を正しく理解し、配信者へのリスペクトを忘れずに、あなたらしいオリジナリティあふれる動画制作を楽しんでください。