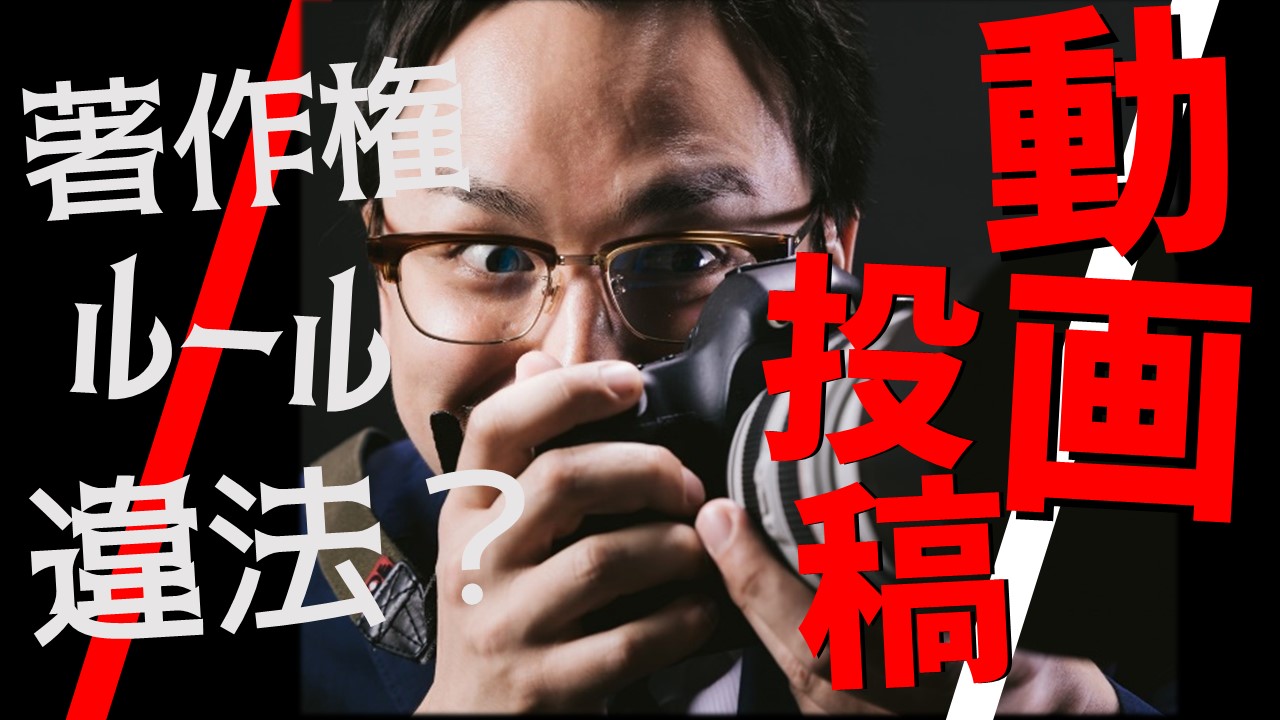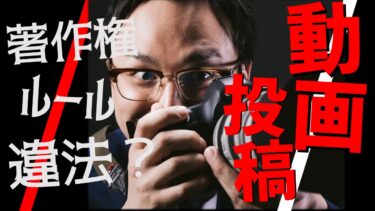「あの配信者、アンチの個人情報や、どんな動画を見てるかまで分かるって言ってたんだけど、本当…?」
もしあなたがそんな噂を耳にして、不安に感じているとしたら、この記事はまさにあなたのために書かれたものです。
YouTubeやX(旧Twitter)で活動する配信者が、視聴者の個人情報(本名、住所、電話番号、さらには他の閲覧履歴まで)を知り得るという話。
真剣に受け止めると、SNSでの行動が委縮してしまいますよね。
配信者がなぜそのような発言をするのか、そして、どのような場合にあなたの情報が明らかになる可能性があるのか、その背景にはいくつかの真実と誤解が隠されています。
この記事では、この「個人情報特定疑惑」について、デマと真実を徹底的に解説していきます。SNSを安心して楽しむためにも、ぜひ最後までお読みください。
1. 配信者が「通常」見ることができる情報とは? — 個人は特定できない統計データ
まず、多くの配信者がYouTube Studioの「アナリティクス」やXの「アナリティクス」といった機能を使って、自分のコンテンツに関する様々なデータを分析しています。
しかし、ここで見られるのはあくまで「個人が特定できない統計情報」に過ぎません。
具体的にどのような情報が見られるのか見てみましょう。
YouTubeの場合
- 視聴者の年齢層
例:「25~34歳が最も多く、全体の40%を占める」 - 性別の割合
例:「男性が70%、女性が30%の割合で視聴している」 - 視聴者がいる国や地域
例:「日本からの視聴が8割、アメリカからの視聴が1割」 - 視聴時間や視聴回数の推移
チャンネル全体や特定の動画がどれくらい再生されたか - トラフィックソース
どこから動画にアクセスがあったか(YouTube検索、関連動画、SNSなど) - 動画の視聴維持率: どの部分で視聴者が離脱しやすいか
これらのデータは、配信者が「どのような層に、どのように動画が届いているのか」を把握し、今後のコンテンツ制作に役立てるためのものです。
例えば、「若い女性の視聴者が多いから、彼女たちが興味を持ちそうな企画を考えよう」といった具合です。
しかし、これらのデータから「東京都に住む〇〇さん(本名)が、この動画を〇時間〇分見て、その後Aチャンネルの動画を5本見た」といった、特定の個人の活動履歴を追跡することは一切できません。
X(旧Twitter)の場合
Xの「アナリティクス」でも、以下のようなデータが確認できます。
- ツイートのインプレッション数
自分のツイートがユーザーのタイムラインに表示された回数 - エンゲージメント数
いいね、リツイート、リプライ、クリックなど、ユーザーが反応した回数 - フォロワーの属性
フォロワーの興味関心や居住地(これも統計データとして) - 最もパフォーマンスの高かったツイート
YouTubeと同様に、これらの情報はアカウント全体のパフォーマンスを示すものであり、個々のユーザーがどのツイートを見て、何に反応したか、その人のアカウント名以外の個人情報はどうか、といった具体的な情報は一切開示されません。
2. 配信者があなたを「個人として認識できる」唯一のケース — あなたが自ら公開した場合
配信者があなたを「個人」として認識できるのは、あなたが自ら、自分のアカウントを介して何らかのアクションを起こし、その際に公開される情報(アカウント名、プロフィールアイコンなど)を目にした場合のみです。
具体的には、以下のような行動が挙げられます。
- コメントを投稿する
- ライブ配信中にチャットを送信する
- スーパーチャット(投げ銭)を送る
- チャンネルメンバーになる(YouTube)
- リプライやDMを送る(X)
これらの場合、配信者はもちろん、その場にいる他の視聴者やフォロワーも、あなたの「YouTubeのチャンネル名(アカウント名)」や「Xのユーザー名」と、あなたが設定している「プロフィールアイコン」を目にすることになります。
もしあなたが、それらのアカウント名やアイコンに本名、顔写真、または個人を特定できる情報を設定しているのであれば、それはあなたが「自ら公開している情報」として認識されます。
しかし、これらはあくまであなたが「公開している情報」であり、配信者が「システムを使って裏で個人情報を抜き取った」わけではありません。
ほとんどのユーザーは匿名性の高いアカウント名で利用しているため、通常はこれだけで身元が特定されることはありません。
3. 「配信者がわかる」発言の真意① — 法的手続き「発信者情報開示請求」
では、なぜ一部の配信者は「アンチの個人情報がわかる」と公言するのでしょうか?
その背景にある最も有力な根拠が、「発信者情報開示請求」という法的な手続きです。
これは、インターネット上で誹謗中傷、名誉毀損、プライバシー侵害、著作権侵害、営業妨害などの「権利侵害」を受けた人が、その投稿者の情報を開示するよう求めることができる制度です。
「単なるアンチコメント」と「法的な権利侵害」の境界線は非常に難しいですが、例えば以下のようなケースが発信者情報開示請求の対象となり得ます。
- 公然と事実ではないことを述べ、配信者の名誉を傷つける
- 個人情報(本名、住所、勤務先など)を晒す
- 殺害予告や脅迫めいたメッセージを送る
- 差別的な発言を繰り返す
発信者情報開示請求の具体的な流れ
この手続きは非常に複雑で、個人が簡単にできるものではなく、専門家(弁護士)の協力が不可欠です。おおまかな流れは以下の通りです。
- サイト管理者(YouTubeやX)への情報開示請求
まず、権利侵害があった投稿が書き込まれたプラットフォーム(YouTubeやXの運営会社)に対して、その投稿者の「IPアドレス」と「タイムスタンプ」の開示を裁判所を通じて求めます。IPアドレスは、インターネット上の住所のようなもので、投稿者がどこからアクセスしたかを示す情報です。 この段階で、投稿の内容が法的な権利侵害に該当するかどうかが厳しく審査されます。 - プロバイダの特定
開示されたIPアドレスから、その投稿者が利用しているインターネットサービスプロバイダ(ISP、例:NTT、ソフトバンク、KDDI、楽天モバイルなど)を特定します。 - プロバイダへの情報開示請求
特定したプロバイダに対して、そのIPアドレスを利用していた契約者の「氏名」「住所」「電話番号」などの個人情報を開示するよう、再び裁判所に申し立てます。ここでも、情報の開示が認められるかどうかの厳密な審査が行われます。
これらのステップを経て、最終的に裁判所に認められれば、権利侵害を行った投稿者の氏名や住所といった個人情報が明らかになる可能性があります。
つまり、配信者が「わかる」と発言するのは、このような法的な手続きを経て、悪質な権利侵害者の身元を特定できるという意味合いが強いと考えられます。
通常の配信者が自分のPC画面からクリック一つで個人情報を見られるわけでは決してありません。
4. 「配信者がわかる」発言の真意② — アンチ行為への「牽制」
もう一つの可能性として、配信者が「アンチの個人情報がわかる」と公言するのは、悪質なコメントや嫌がらせ行為に対する「牽制」や「ハッタリ」であることも考えられます。
「変なことを書き込むと身元がバレるかもしれない」という心理的なプレッシャーを与えることで、アンチコメントを抑制し、健全なコミュニティを維持しようとする狙いがあるのかもしれません。
これは特に、誹謗中傷に悩まされている配信者にとっては、視聴者との関係性を守るための有効な手段となり得ます。
もちろん、この発言が全てを真実として語っているわけではなく、一種の「パフォーマンス」であることも理解しておくべきでしょう。
5. 「他のどんな動画を閲覧していたか」という情報について — ほぼ100%デマ
さて、ご質問の中には「アンチが他にどんな動画を閲覧していたか」という情報まで配信者が知っているか、という点がありました。
この点については、ほぼ100%デマであると断言できます。
前述の「発信者情報開示請求」は、権利侵害があった投稿と、その投稿者の「最低限の身元情報」を開示することを目的としています。
個人のウェブサイト閲覧履歴や視聴履歴といった情報は、「通信の秘密」や「プライバシー権」によって高度に保護されているため、仮に誹謗中傷などの権利侵害があったとしても、それとは直接関係のない「他の閲覧動画」まで開示が認められることは、まずありません。
これは、あなたが誰かの誹謗中傷を行ったとしても、その罪とは全く関係のない「あなたの普段の行動や趣味嗜好」が、被害者や第三者に開示されてしまうことはない、というのと同じ論理です。
したがって、配信者が「アンチの他の閲覧動画がわかる」と発言しているとしたら、それは誤解に基づいた発言か、意図的な誇張表現である可能性が極めて高いと言えるでしょう。
6. SNSを安心して楽しむために — 私たちができること
ここまでの解説で、YouTubeやXの配信者が、通常の機能であなたの個人情報を知ることはなく、特別な法的手続きを踏まない限り身元は特定されないことがご理解いただけたかと思います。
SNSを安心して楽しむために、私たち視聴者やユーザーができることは以下の通りです。
- アカウント名とプロフィールアイコンに個人情報を含めない
本名、顔写真、住所の一部、電話番号、勤務先が特定できる情報などは、公開アカウントで使わないようにしましょう。匿名性の高いニックネームやイラストアイコンの利用をお勧めします。 - コメントやチャットの内容に注意する
節度ある発言を心がけましょう。たとえ匿名のつもりでも、過度な誹謗中傷や脅迫は法的なリスクを伴います。 - プライバシー設定を確認する
各SNSには、自分の投稿の公開範囲や、個人情報の共有設定を行うプライバシー設定があります。定期的に確認し、意図しない情報公開がないかチェックしましょう。 - 個人情報を求める怪しいメッセージに警戒する
「抽選に当たったから住所を教えて」「〇〇の企画で個人情報を確認したい」など、不審なメッセージには安易に返信せず、公式からの連絡か、詐欺の可能性がないか慎重に判断しましょう。
まとめ
改めて、今回のポイントをまとめます。
- YouTubeやXの通常の機能で、配信者が視聴者の本名、住所、電話番号、他の閲覧履歴といった個人情報を知ることはできません。見られるのは、個人を特定できない統計情報のみです。
- 配信者が「わかる」と発言する場合、それは「発信者情報開示請求」という法的な手続きを経て、悪質な権利侵害者の身元を特定できる可能性がある、という意味合いが強いです。
- 「アンチの他の閲覧動画がわかる」という話は、法的に開示される可能性が極めて低く、デマや誇張表現であると考えられます。
- あなたが自ら、アカウント名やプロフィールに個人情報を含めて公開している場合のみ、配信者や他のユーザーにその情報が認識される可能性があります。
インターネットは匿名で利用できる側面がある一方で、悪質な行為に対しては法的な責任が問われることもあります。
しかし、必要以上に恐れることなく、正しい知識を持って利用すれば、SNSは私たちの生活を豊かにしてくれる素晴らしいツールです。
この情報が、あなたがSNSをより安心して楽しむ一助となれば幸いです。