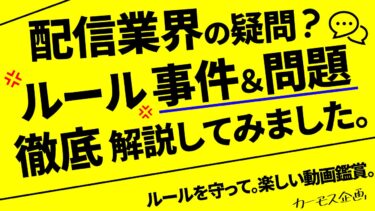ネットニュースやSNSを開けば、今日も誰かが「炎上」している。
芸能人や政治家だけでなく、YouTuber、VTuber、あるいは一般の個人アカウントまで、その対象は広がり続けています。
もはやネットの炎上は珍しい事件ではなく、日常の風景となりつつあります。
なぜ、これほどまでにネットの炎上は絶えないのでしょうか?
今回はその背景にある構造的な理由を掘り下げてみたいと思います。
「他人のウワサ話」への尽きない需要
まず大前提として、私たちは「他人のスキャンダルや失敗談」に強く惹きつけられる性質を持っています。
これは今に始まったことではありません。
学生時代、「隣のクラスの〇〇さんが、こんなことをしたらしい」といったウワサ話に花が咲いた経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。
こうした話題は、手軽なコミュニケーションの潤滑油であり、一種のエンターテインメントとして機能します。
この「他人のミスや秘密を共有したい」という欲求こそが、炎上という現象が成立する根底にあるのです。
つまり、「炎上ネタ」には常に確実な需要が存在します。
「炎上」をビジネスに変えるメディアの存在
強い需要があれば、そこには必ずビジネスが生まれます。
ゴシップ週刊誌が有名人のスキャンダルを追い続けるのと同じように、ネット上では個人の炎上を記事化し、アクセス数を稼ぐ「まとめサイト」やニュースブログがその役割を担っています。
彼らは炎上の火種を見つけると、それを分かりやすい「ニュース」としてパッケージ化します。
そして、SNSを通じて拡散させることで、莫大なページビュー(PV)と広告収入を得るのです。
有名人の名前を検索すると、予測変換に「炎上」「批判」といった言葉が並ぶことからも、どれだけ多くの人がその話題を求めているかがわかります。
この巨大な需要がある限り、炎上を記事化するメディアが消えることはありません。
エスカレートする「炎上」の燃料投下
炎上記事で収益を上げるメディアは、常に新しい「燃料」を求めています。
一つの炎上が鎮火すれば、すぐに次の炎上を見つけなければなりません。
その結果、彼らは次第により過激で、より些細な火種を探し求めるようになります。
かつては明確な不祥事や問題発言が炎上の対象でした。
しかし今では、「少し失言に聞こえる言葉」や「賛否が分かれる意見」といったレベルでも、いとも簡単に「炎上」として報じられます。
数件の批判的なコメントを意図的に抜き出し、「〇〇に批判殺到!」といった扇情的な見出しをつける。
これは彼らの常套手段です。
こうして、本来であれば小さな意見の対立で終わるはずだったものが、世間を巻き込む大事件へと仕立て上げられていくのです。
「炎上なき時代」が「炎上を作り出す」時代へ
5年前(2020年ごろ)、私はこの記事と同じような記事を書いていました。
そのときの私は「YouTuberやVTuber界隈はまだ未熟で、自然発生的な炎上が多い」と述べました。
しかし現在、状況は大きく変わりました。
多くのクリエイターや企業はコンプライアンス意識を高め、不用意な発言や行動を避けるようになっています。
つまり、「自然に燃える」ことは明らかに減ってきているのです。
では、炎上メディアはどうしたか?
答えは単純で、「炎上を自ら作り出す」ようになりました。
意見が少し割れる発言を切り取っては「大論争」と報じ、誰かがルールやマナーについて少しでも苦言を呈せば「〇〇の発言がSNSで炎上!」と煽る。
もはや、彼らにとってはすべてが「炎上の種」です。
悪質なケースでは、自作自演で批判的なコメントを書き込み、それを元に記事を作成している可能性すら否定できません。
これは、週刊誌がターゲットを陥れるために「ハニートラップ」を仕掛ける構造とよく似ています。
ネット上では、誰もがこの「炎上トラップ」のターゲットになり得るのです。
まとめ:私たちは「炎上ビジネス」の渦中にいる
この記事で見てきたように、ネットの炎上は単なる個人の感情的なぶつかり合いではありません。
そこには「人間のゴシップ欲求」を土台とし、「メディアによる収益化」というエンジンによって駆動される、巨大なビジネス構造が存在します。
私たちは、その構造のまっただ中で生きています。
正直なところ、かつてのような純粋なエンターテインメントとしてインターネットを楽しむことは、年々難しくなっていると感じます。
しかし、この構造を理解することで、私たちにできることもあります。
それは、目にする情報を鵜呑みにせず、「この記事は誰が、何のために書いたのか?」と一歩引いて考える癖をつけることです。
情報の取捨選択が、かつてないほど重要になる時代。
過剰な扇動に踊らされず、自分自身の心を守るための「デジタルリテラシー」が、今、私たち一人ひとりに求められています。