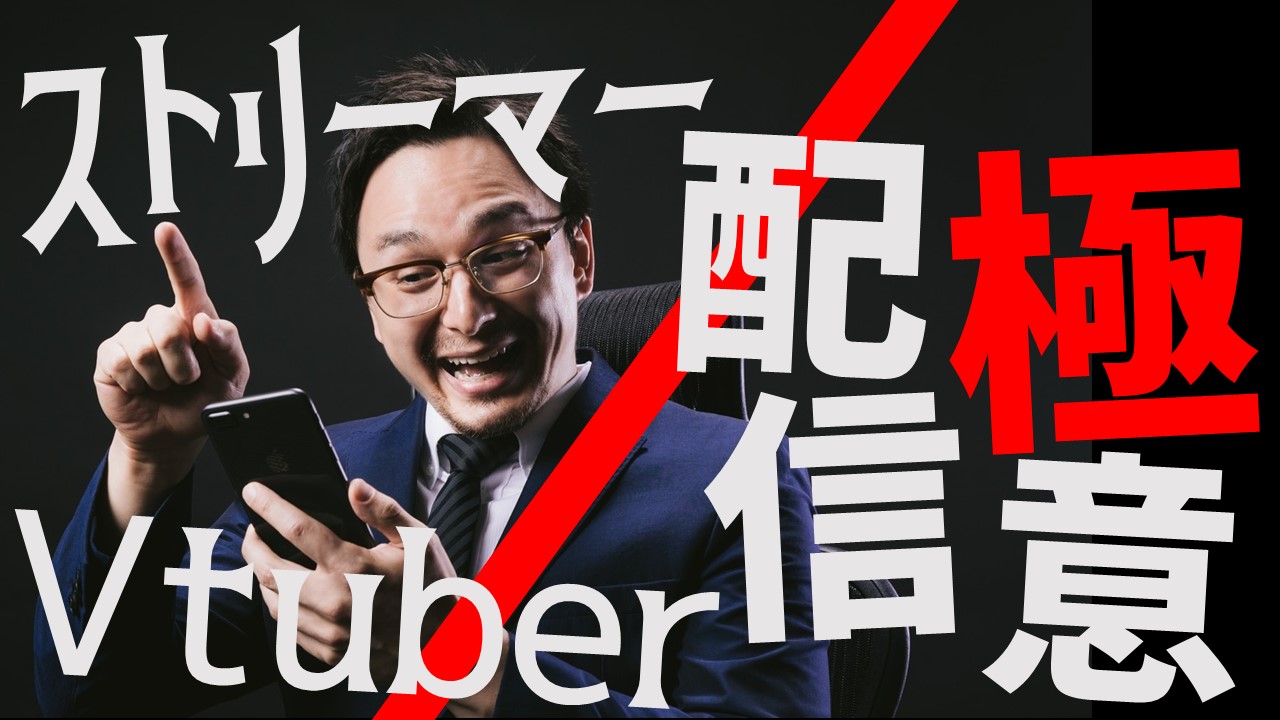大勢の人気ストリーマーやVtuberが、ひとつのゲーム世界に集結し、1ヶ月にわたって人間ドラマを繰り広げる――。
「MADTOWN」に代表される大規模ストリーマーイベントは、予測不能な事件が起こり、感動的な物語が生まれます。
しかし、その熱狂の裏側で、私たちはある種の「息苦しさ」を感じてはいないでしょうか。
コメント欄には些細なことで激しい言葉が飛び交い、参加している配信者たちは「炎上しないように」と、まるで薄氷の上を歩くかのようにプレイする姿が見られます。
「たかがゲームのお遊びじゃないか」
「どうして、みんなそんなにマジになって怒るんだ?」
多くの人が抱くこの素朴な疑問…。
なぜ「お遊び」は「戦場」に変わるのか? 視聴者が熱くなる5つの理由
そもそも、なぜ視聴者は「お遊びのゲームイベント」に、これほどまでに感情を揺さぶられてしまうのでしょうか。
そこには、視聴者がイベントを単なる「ゲーム観戦」として捉えていない、という事実があります。
1. 画面の向こうは「推し」が生きるドラマの世界
多くのストリーマーイベント、特にGTAのようなゲームでは「ロールプレイ(RP)」が中心となります。
参加者はゲーム内のキャラクターを演じ、視聴者はそのキャラクターが織りなす物語に没入します。
これはもはやゲーム配信ではなく、一種の「リアルタイム連続ドラマ」です。
私たちは、自分の好きな配信者が演じるキャラクターに感情移入し、その活躍に一喜一憂し、困難に立ち向かう姿を応援します。
問題は、この没入感が深すぎるあまり、一部の視聴者が「キャラクター」と「配信者(中の人)」を混同してしまう点にあります。
ゲーム内でキャラクターが誰かに騙されたり、理不尽な目に遭ったりすると、まるで自分の好きな配信者自身が侮辱されたかのように感じ、怒りを覚えてしまうのです。
「うちの推しに何てことを!」という怒りは、キャラクターではなく、相手役を演じている配信者本人へと向かっていきます。
2. 「推しを守りたい」という強すぎる気持ち
視聴者にはそれぞれ「推し」がいます。
この「推し」を応援する気持ちは、時に過剰な防衛心理へと変化します。
自分の推しがゲーム内で不利な状況に陥ると、ファンは「自分の推しが損をしている」「不当な扱いを受けている」と感じ、まるで自分がその被害を受けたかのような「当事者意識」を持ちます。
この意識がエスカレートすると、いつしか「推しの配信者 vs 他の配信者」という構図が、「自分のファンコミュニティ vs 他のファンコミュニティ」というファン同士の代理戦争に発展してしまうのです。
相手の配信者のコメント欄に乗り込んで文句を言う「鳩行為」は、まさにこの心理の表れです。
「推しを守れるのは自分たちしかいない」という歪んだ使命感が、攻撃的な行動の引き金となります。
3. 文脈を無視した「切り抜き」という名の凶器
1ヶ月にも及ぶ長期間のイベント。すべての配信者の視点をリアルタイムで追いかけることは物理的に不可能です。
そのため、多くの視聴者は、特定の場面だけを抜き出した「切り抜き動画」で情報を補完します。
この切り抜き文化は、イベントの面白さを広く伝える一方で、深刻な問題もはらんでいます。
それは「文脈の欠如」です。
ある過激な行動に至るまでには、その前段階として様々なやり取りや伏線があったかもしれません。
あるいは、当事者同士では「プロレス」として合意の上だったかもしれません。
しかし、切り抜き動画は、そうした前後の文脈をバッサリと切り捨て、最も衝撃的な場面だけを映し出します。
さらに、再生数を稼ぐために「【悲報】〇〇、非道な裏切り!」といった扇情的なタイトルがつけられることで、視聴者はたった数十秒の映像だけで物事を判断し、「あいつはひどいヤツだ」という誤った認識を植え付けられてしまうのです。
4. 匿名性が生み出す「無敵の自分」
インターネット、特にコメント欄という匿名性の高い空間は、人々の攻撃性を増幅させる装置として機能します。
普段の社会生活では決して口にしないような罵詈雑言も、匿名の仮面を被ることで、何の抵抗もなく書き込めてしまいます。
さらに怖いのは「集団心理」です。
誰かが批判的なコメントを書き込むと、「自分もそう思っていた」「よく言った!」と同調する人々が現れ、あっという間に大きな世論のようなものが形成されます。
一人では言えないような過激な言葉も、「みんなも言っているから」という免罪符を得ることで、正当化されてしまう。
こうして、個々の小さな不満は、集団の巨大な悪意へと膨れ上がっていくのです。
5. 「俺たちのイベント」という歪んだ帰属意識
熱心な視聴者は、自分を単なる「観客」だとは思っていません。
長期間イベントを追いかけ、コメントやスーパーチャットで配信者を応援するうちに、「自分もこのイベントを一緒に作っている一員だ」という強い帰属意識を持つようになります。
この意識自体は、コミュニティの熱量を高めるポジティブな要素です。
しかし、これが歪んだ方向に進むと、「イベントはこうあるべきだ」「あの参加者の行動は、この素晴らしいイベントの空気を乱している」といった過剰な当事者意識につながります。
「俺たちのイベントを守るため」、彼らは特定の参加者を排除しようと、批判の声を強めていくのです。
「ルール警察」はなぜ生まれるのか? “正義”が暴走するメカニズム
コメント欄の荒れの中でも、特に厄介視されがちなのが「ルール警察」の存在です。
「今の行動はルール違反だ!」「その発言ってルール的にダメじゃない?」と、彼らは執拗に参加者のプレイを監視し、断罪します。
プロの競技シーンでもないのに、なぜ彼らはそこまで厳格なルールを求めてしまうのでしょうか。
プロの大会ではない「からこそ」求められる絶対的な公正さ
逆説的ですが、ストリーマーイベントがプロの大会ではないからこそ、ルール警察は生まれます。
プロのeスポーツ大会には、絶対的な権威を持つ「審判」や「運営」が存在します。
彼らが下すジャッジがすべてであり、ファンが介入する余地はありません。
しかし、ストリーマーイベントでは、運営の目が隅々まで行き届かないことも多く、明確な裁定が下されないグレーな場面が多々あります。
この「権威の空白」を埋めようとするのが、一部の視聴者なのです。
「運営が見ていないのなら、俺たちが監視し、裁きを下さなければならない」という歪んだ正義感や義憤が、彼らをルール警察へと変貌させます。
彼らは、イベントの「公正さ」を自らの手で守っていると信じているのです。
「メタ警察」の正体――物語の世界観を守りたい防衛本能
ルール違反の中でも特に視聴者の怒りを買いやすいのが「メタ発言」です。
なぜなら、メタ発言は、視聴者が没入している「物語(ドラマ)」の世界観を根底から破壊する行為だからです。
キャラクターとして会話していたはずの人物が、突然「昨日の配信でさ…」と配信者としての顔をのぞかせた瞬間、視聴者は一気に現実へと引き戻されます。
「ああ、これはやっぱりただのゲームなんだ」と冷めてしまうのです。
この「冷めてしまう」感覚に対する嫌悪感が、「俺たちの楽しんでいる世界を壊すな!」という強い防衛本能となり、メタ発言をした参加者への厳しい攻撃につながります。
3. 心の中では済まされない。「コメント」で戦う理由
「ルール違反だと思っても、心の中で思うだけでいいじゃないか」――そう思う人も多いでしょう。
しかし、彼らがわざわざコメントで指摘し、時にはレスバトルにまで発展させるのには、いくつかの心理的要因があります。
- 正義の実行という快感(正義中毒)
「悪いこと(ルール違反)を見つけ、それを公の場で指摘し、正す」という行為は、一部の人に強い快感と自己肯定感をもたらします。
「自分は正しいことをしている」という感覚に酔いしれ、それが癖になってしまうのです。
この快感は、他者を断罪することで最大化されます。
- 推しを守るための「騎士(ナイト)」行為
彼らにとって、コメントでの指摘は単なる文句ではありません。
それは、ルール違反によって不利益を被った(と彼らが感じている)推しを守るための「戦い」なのです。
「自分がここで声を上げなければ、推しが損をしたままになる」という過剰な使命感が、彼らをキーボードに向かわせます。
- 承認欲求と「いいね」の魔力
勇気を出して(と本人は思っている)指摘コメントをすると、「それな!」「よく言った!」という同調のコメントや「いいね」が集まります。
仲間からの支持によって承認欲求が満たされ、「自分の意見はコミュニティの総意だ」と錯覚し、発言はさらに過激化していきます。
まとめ
ここまで見てきたように、ストリーマーイベントの熱狂とコメント欄の荒廃は、表裏一体の関係にあります。
視聴者の深い没入感や推しへの愛情が、イベントを最高に面白いものにしている一方で、その熱量が少しでも道を誤ると、途端に配信者を傷つける刃へと変わってしまうのです。
この状況がもたらす最悪の結末は「配信者の萎縮」です。
常に炎上を恐れ、「これをやったら叩かれるかもしれない」と行動が制限される。
結果として、誰もが当たり障りのないプレイに終始し、イベント本来の魅力であるハプニングや化学反応が失われていく…。
この悪循環こそが、私たちが感じている「息苦しさ」の正体です。
では、一人の視聴者として、私たちは何ができるのでしょうか。
もし、イベントを純粋に楽しみたいと願うなら、できることはあります。
-
一呼吸置く: 怒りや不満を感じても、すぐにコメントしない。本当にその言葉を今、ここに書く必要があるのか、一度冷静に考えてみる。
-
多角的な視点を持つ: 自分の推しの視点だけでなく、相手の視点の配信や前後の文脈を確認する努力をする。物事の一部分だけで判断しない。
-
ポジティブな声を増やす: 批判的なコメントを打ち消すように、「今のプレイ最高!」「面白い!」といったポジティブなコメントで、チャット欄の空気を良くしていく。
-
通報・ブロック機能を活用する: 明らかに悪意のある誹謗中傷は、相手にせず、プラットフォームの機能を使って粛々と対処する。
MADTOWNのようなイベントは、配信者と視聴者が一緒になって作り上げる、現代ならではの素晴らしいエンターテインメントです。
その灯火を、一部の過剰な熱によって消してしまわないために。
私たち一人ひとりが、画面の向こうにいるのが感情を持った一人の人間であることを忘れず、敬意を持ってこの「お祭り」に参加することが、何よりも大切なのかもしれません。