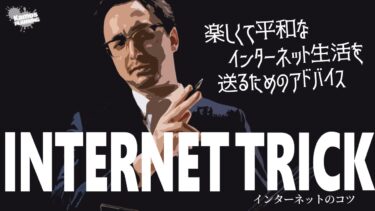にじさんじから新人ライバーがデビューする。それは、ファンにとって心躍る一大イベントです。
どんな個性を持った人が現れるのか、どんな新しい物語が始まるのか。期待に胸を膨らませ、デビュー配信を見守る時間は、このカルチャーを愛する者にとってかけがえのないものです。
しかし、そんな祝福ムードに包まれるはずのタイムラインで、私たちは時折、ある種の違和感を覚える言葉を目にします。
「なんだか、にじさんじらしさがないな」
デビューしたばかりの新人に向けて放たれるこの一言。
多くの場合、その言葉は具体的な批評ではなく、漠然とした印象論に終始します。
この発言に対し、「わざわざ今言う必要がない」「空気が読めない」と不快感を覚えたり、モヤモヤした気持ちになったりする方も多いのではないでしょうか。
そもそも「にじさんじらしさ」とは何か?
この問題を考える上で、まず定義しなければならないのは「にじさんじらしさ」という、極めて曖昧な言葉そのものです。
あなたにとっての「にじさんじらしさ」とは何でしょうか?
-
1期生や2期生、SEEDsが活躍した初期の、技術トラブルさえも笑いに変える「学園祭」や「サークル活動」のような手作り感とカオスな雰囲気でしょうか。
-
あるいは、個性豊かなライバーが次々とデビューし、尖った企画やプロレス、感動的な「てぇてぇ」関係性など、予測不能なエンターテイメントが爆発的に生まれた「多様性の坩堝」としての側面でしょうか。
-
それとも、今や巨大な企業となり、クオリティの高い3Dライブや大規模なイベント、メディアミックスなどを展開する、洗練された「総合エンタメコンテンツ」としての姿でしょうか。
おそらく、答えは一つではありません。ファンの数だけ「にじさんじらしさ」の解釈は存在します。
重要なのは、「にじさんじらしさ」とは固定された概念ではなく、新しいライバーがデビューするたびに更新され、拡張され、その意味合いを変化させ続けてきたという事実です。
黎明期のカオスも、成長期の多様性も、現在の洗練された姿も、すべてが「にじさんじらしさ」を構成する大切な要素なのです。
それにもかかわらず、「らしさがない」と断じる人々は、この流動的な概念を、自分の中の特定の時代のイメージに固定してしまっているのかもしれません。
「らしさがない」発言の裏にある5つの深層心理
では、彼らがその言葉を口にする背景には、どのような心理が働いているのでしょうか。
それは一つではなく、いくつかの感情が複雑に絡み合っています。
ノスタルジーと古参意識
これが最も根源的な感情であり、まさしく「昔は良かった」論の核となる部分です。
彼らの多くは、にじさんじの初期、まだコミュニティが小さく、ライバーとリスナーの距離が近かった時代に強い愛着を持っています。
荒削りであっても、そこには確かに「自分たちがコンテンツを一緒に育てている」という熱狂と一体感がありました。
彼らにとって、その時代の記憶は強く美化されています。いわゆる「思い出補正」です。
企業の成長に伴い、システムが整備され、デビューする新人がそつなく配信をこなす姿は、彼らの目には「完成されすぎている」「手作り感がない」と映ります。
自分たちが愛したあの頃の「原風景」が失われていくことへの寂しさや喪失感が、「にじさんじらしさがない」というノスタルジックな言葉になって表出するのです。
変化への抵抗とコミュニティ防衛本能
人間は本能的に、慣れ親しんだ環境の変化を恐れる生き物です。
にじさんじという巨大なコミュニティも例外ではありません。
新しいライバーが増えるということは、既存のライバーとの関係性が変わり、ファンコミュニティの雰囲気や「ノリ」が変化する可能性を意味します。
自分の知らないファン層が流入してくることへの警戒心も生まれます。
「自分たちの愛したコミュニティが、知らない人たちに乗っ取られてしまうのではないか」
「居心地の良かった場所が変わってしまうのではないか」
といった無意識の不安。
その不安が、変化の象徴である「新人」に対する拒否反応として現れることがあります。
「らしさがない」という言葉は、この変化への抵抗感を正当化するための便利なフレーズなのです。
ゲートキーピング(選民意識)とアイデンティティの確認
「ゲートキーピング」とは、あるコミュニティにおいて古参のメンバーが「何が本物で、何が偽物か」を定義し、新規参入者をジャッジしようとする行動を指します。
「にじさんじらしさがー」という発言の裏には、「自分は黎明期からこのコンテンツを知っている真のファンだ。だから、何が『にじさんじらしい』のかを理解している」という、一種の優越感や選民意識が隠れている場合があります。
彼らにとって、「古参であること」はファンとしてのアイデンティティの一部となっています。
新人ライバーに対して「らしさ」を問う行為は、彼らにとって「自分は新参者とは違う、本質を理解したファンなのだ」と自他に確認するための儀式のようなものです。
新しい才能を評価するのではなく、自分の知識や経験を基準に「テスト」をすることで、コミュニティ内での自身の立ち位置を再確認しようとしているのかもしれません。
理想化された「にじさんじ像」とのギャップ
ファンは誰しも、そのコンテンツに対してある種の「理想」を抱きます。
「にじさんじは尖った企画をする破天荒な集団だ」「感動的な人間ドラマが魅力だ」「歌やゲームが上手い実力派揃いだ」など、人によって惹かれる側面は様々です。
問題は、その特定の側面だけを「にじさんじの全て」であるかのように理想化してしまうことです。
自分の中で凝り固まった理想像と、新しくデビューしたライバーのスタイルが異なっていた場合、彼らはそれを「期待外れ」と認識します。
例えば、尖った芸人タイプを期待していたところに、王道のアイドル的なライバーが現れた場合、「これは自分が求めていたにじさんじではない」と感じてしまうのです。
しかし、にじさんじの本当の魅力は、芸人タイプもアイドルタイプも、ゲーマーもクリエイターも、あらゆる個性が共存する「多様性」そのものにあるはずです。
自分の理想像という狭い物差しで新人を測り、「らしさがない」と切り捨てるのは、コンテンツが持つ本来の豊かさを見失う行為と言えるでしょう。
個人的な「好み」の正当化
最も単純でありながら、見過ごされがちな心理です。
突き詰めれば、その新人ライバーのデザイン、声、話し方、キャラクター性などが「個人的に好みではなかった」だけ、というケースも少なくありません。
しかし、「あなたのことが嫌いです」とストレートに言えば、それは単なる誹謗中傷になってしまいます。
そこで、「にじさんじらしさがない」という言葉を“鎧”として使うのです。
これなら、個人的な好き嫌いを、あたかも箱全体を憂うファンの客観的な意見であるかのように見せかけることができます。
「私個人の感想」を「ファン全体の総意(であるべきもの)」へと主語をすり替えることで、自分の否定的な感情を正当化しようとする心理が働いています。
「昔は良かった」という言葉が、未来の可能性を奪う
ここまで見てきたように、「にじさんじらしさがー」という言葉は、発言者のノスタルジー、不安、プライド、そして個人的な好みが複雑に絡み合った、極めて主観的な感情の表れです。
それは、コンテンツの未来を建設的に考える批評ではなく、過去の美しい記憶にすがる懐古主義に他なりません。
この言葉が問題なのは、単に祝福ムードに水を差すだけでなく、これから羽ばたこうとする新しい才能の可能性の芽を摘みかねないからです。
デビュー直後のライバーは、大きな期待と同時に、計り知れないプレッシャーを感じています。
そんな中で投げかけられる漠然とした否定的な言葉は、彼らの自信を奪い、本来の魅力を発揮する妨げになり得ます。
もし、にじさんじが本当に「らしさ」に固執し、初期のメンバーと同じようなタイプの人材ばかりを集めていたら、どうなっていたでしょうか。
おそらく、ここまで巨大で多様な魅力を持つコンテンツには成長していなかったでしょう。
委員長がいて、でろーんがいて、そこへギルザレンⅢ世が現れ、剣持刀也が異彩を放ち、月ノ美兎とは全く違うタイプの静凛が人気を博す。
その繰り返しが、にじさんじという世界の奥行きをどこまでも広げてきました。
「にじさんじらしさ」とは、過去の誰かのコピーになることではありません。
むしろ、「これまでの『にじさんじらしさ』を打ち破り、新しい『らしさ』を定義してくれるかもしれない」という未知の可能性こそが、新人デビューの最大の醍醐味なのです。
まとめ
もちろん、新人ライバーに対して何も意見を言ってはいけない、ということではありません。
建設的なフィードバックや、応援の気持ちを込めたアドバイスは、彼らの成長の糧になるでしょう。
大切なのは、自分の個人的な感情や過去の思い出を「絶対的な基準」にしないことです。
まずは先入観を捨て、その新人ライバーがこれから見せてくれるであろう、まだ見ぬ個性や物語に目を向けてみませんか。
デビュー配信だけで全てを判断せず、少し長い目で彼らの活動を見守ってみる。
自分の好みとは違ったとしても、その存在を否定するのではなく、「こういう新しい魅力もアリだな」と受け入れてみる。
その寛容さが、にじさんじというコミュニティをより豊かで、より面白い場所に育てていくはずです。
「昔は良かった」と過去を懐かしむ気持ちは、誰にでもある自然な感情です。
しかし、その感情に囚われて未来の可能性を否定してしまっては、あまりにもったいない。
かつての「新人」たちがそうであったように、今、私たちの目の前にいる新人たちも、数年後には「あの人がいてくれて良かった」と言われるような、かけがえのない存在になっているかもしれません。
その未来を信じ、温かい目で見守ること。それこそが、この変化し続けるコンテンツを心から楽しむための、ファンとしての最も「らしい」姿勢なのではないでしょうか。